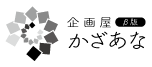日本各地を観光していると、お土産屋さんや展示室にて「伝統工芸」や「民芸」を見かけます。
様々な品が地元文化として継れています。
「伝統工芸品」というと、職人の極めた技術で作られたものをイメージし、「民芸品」は生活のなかで使われたものとして展示されていますが、一体どんなところから生まれた言葉なのでしょうか。
日用的に使われる「工芸品」
「工芸品」とは、大量生産でつくられる工業製品とは異なり、何年もかけて鍛え上げた熟練の技術を駆使してつくられた美的器物をいいます。
「工芸品」の中でも大きく3つに分別され、古来からのカタチのもの、美術性を重視したもの機能性を見出したものがあります。
工芸品は地域の文化風土から誕生した日用使いの手工業製品になります。
そこから、献上品として、はたまた娯楽やお洒落などを追求していくなかで美術性の高い「美術工芸」というものが生まれてきます。
どうしても手間ひま、日数がかかることから、工芸品は単価が高くなります。
それゆえに高額で売れる「美術工芸」を作ることを目指すことが多いです。
しかし、高額な工芸品ばかり作っていては、一般庶民からは遠い存在となり興味も抱かれず、継承する人材も流入してこなくなってしまいます。
経済産業省では日用品に使われるものを「伝統的工芸品」と認めています。
また、現在ではアナログ回帰、自然志向の方が増え見直されてきていることから、暮らしの中に役に立つ機能性をもった「近代工芸」とよばれる「工芸品」が出てきています。
「民芸品」は民衆のなかで生まれた
「民芸品」とは造語のようで元は「民衆的工芸品」と呼ばれ、民衆が生活していくなかで、暮らしの身近にある地元にある材料を使い、知恵と経験でつくられてきたものです。
「民藝」という言葉を提唱した柳らによれば、そこに見られる9つの特性をあげています。
- 実用性。鑑賞するためにつくられたものではなく、なんらかの実用性を供えたものである。
- 無銘性。特別な作家ではなく、無名の職人によってつくられたものである。
- 複数性。民衆の要求に応えるために、数多くつくられたものである。
- 廉価性。誰もが買い求められる程に値段が安いものである。
- 労働性。くり返しの激しい労働によって得られる熟練した技術をともなうものである。
- 地方性。それぞれの地域の暮らしに根ざした独自の色や形など、地方色が豊かである。
- 分業性。数を多くつくるため、複数の人間による共同作業が必要である。
- 伝統性。伝統という先人たちの技や知識の積み重ねによって守られている。
- 他力性。個人の力というより、風土や自然の恵み、そして伝統の力など、目に見えない大きな力によって支えられているものである。
このような特性があげられています。
民藝運動により生まれた「民藝」
伝統工芸品に興味がある方は一度は耳にしたことがあるインダストリアルデザイナー柳宗理。
彼の父であり思想家である柳 宗悦(やなぎむねよし)が提唱したことにより、「民藝」という言葉は生まれました。
1889年生まれである柳 宗悦は、西洋美術を紹介する美術館を建設しようと、数々の作品を蒐集をしていました。
そんななか、客人の手土産にもってこられた壺を見て、工芸品に魅了されていきます。
1925年(大正14年)に「民藝」という言葉を使い、翌年1926年に陶芸家の富本憲吉、濱田庄司、河井寛次郎の四人の連名で「日本民藝美術館設立趣意書」を発表しました。
これにより「民藝」という言葉が使われるようになり、手仕事で作られた日常的な暮らしの中で使われる「用の美」を見出しました。
その後、日本独自の運動となる「民藝運動」は、当時の美術界では注目されなかった民衆的工芸品に真の美を見出し、世間に紹介していく活動をはじめ調査・収集に尽力しました。
「工芸」と「民芸」の言葉の歴史
民衆が自分たちで使うものとして自分たちでつくってきたものが「民芸品」で、その後、物々交換などに発展し、より優れた技術が必要なものや差別化されたものに発展したことで「工芸品」となっていったと考えられますが、言葉自体は「工芸」が先にあったようです。
「工芸」という言葉は、1885 年(明治 18)東京帝国大学に「工芸学部」が設置された際に示されていますが、明治時代では「工芸」は「工 業」の意味で使用されていることがあったそうです。
そして、その後1926年に民藝運動による「民藝」という言葉が生まれました。
ですので、「工芸」も「民芸」も最近になって生まれた言葉で、思想や時代背景により変わってきているため、色々な論点や定義が生まれてきてしまっているようです。
あまり言葉にとらわれすぎると、その品の真髄を見出すことができなくなってしまいますので、ただその品を見て使って、用の美、感の美を愉しむことがよいのではないでしょうか。
<関連記事:「用の美」「感の美」をもつ伝統工芸の7つの要素>
関連サイト: